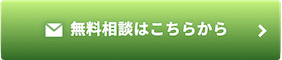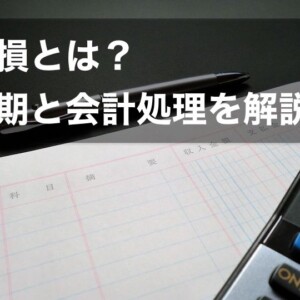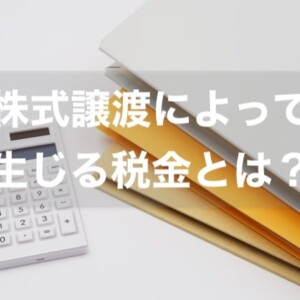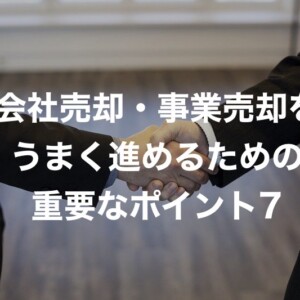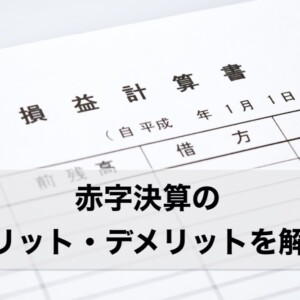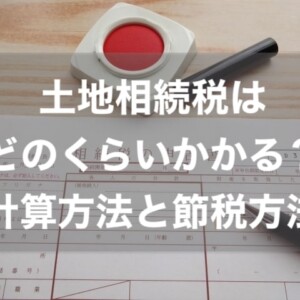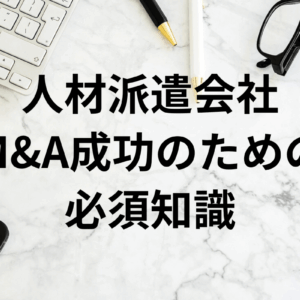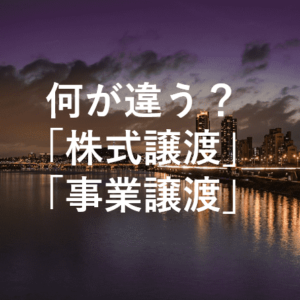事業承継の心得とは|オーナー経営者は後継者に「自分の分身」を求めてはいけない
創業者によって始められた事業が時を経るごとに成長していったとしても、その創業者がずっと事業を継続できるわけではありません。
残念ながら人の一生は限られてるからです。また、仮に永遠の命をもって事業を続けられるとして、同一事業が同じように継続するとは考えづらいとも思います。
なぜなら、時代は常に変化し、求められるものはそのときどきによって変化するわけで、どうしても同じ人ひとりでは到底対応しきれるものではありません。「時代に合わせた変化が必要だ」と言いながら、実情はそれを理解しきれていない経営者は多いものです。
事業承継というのが体系化されたものではなく、また計画的になされているわけではないので、致し方ないとも言えるでしょう。もし事業承継が先の課題だったとしても、来るべき事業承継のタイミングに向けて、自分以外の人間に事業を承継するということをイメージして、変えてほしくないもの、変えたほうがよいもの、をぜひ冷静に想像してみてほしいと思います。
CONTENTS
事業の継続には必ず「変化」が必要
It isn’t the strongest of the species that survive,nor the most intelligent but the ones most responsive to change.
『最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残ることが出来るのは、変化できる者である。』
というのはダーウィンの言葉ですが、進化論を唱えるなかで、一番重要なものを「変化」として捉えています。
周知のとおり、生物は太古より姿形を変えながらそのときどきの状況や環境に適応した形で変化をしながら生き延びてきたわけですが、生命や生物という壮大な話でなくとも、目の前のものひとつとっても変化の目まぐるしいことか。そして、変化しながら残っているもの、変化せずに消えてしまったものに気付かされるのではないでしょうか。
企業が当たり前に扱う商品もまた流行があり、寿命があります。
時代によって、環境によって、人間のライフスタイルによっても変化するものですから、当然ともいえますが、こうした変化に対応できる企業は残り、対応できなければ消えていく。変化をとらえ、実際に変化をするということが企業存続の文字通り生命線となるのです。
たとえば、変化しながら継続する企業としては富士フィルはあまりにも有名です。
写真フィルムを主力事業としながら、時代はデジタルの波が来ていました。時代に求められているとはいえ、自社でデジタルを推進するのは、フィルムという伝統もあり思い入れもある既存事業を破壊していくというジレンマを抱えるもの。競合がモラトリアムに陥り変化の手を休めるなか、富士フィルムはデジタルカメラへの挑戦を先頭切って推進。競合は破産、富士フィルムは時代に合わせた変化を遂げ生き残りました。その後もフィルムに使用した技術をヘルスケア業界に転用、医療業界へ進出し、イノベーション企業の代名詞のような存在になっています。
もう少し身近なところでいえば、和菓子屋、酒屋、蕎麦屋など伝統とともに生き、何代も続く「老舗」と言われる飲食店も同様に変化しているのです。
たとえば、江戸時代は1707年創業の伊勢の赤福。言わずと知れた赤福餅が主力商品で、300年以上も同じ商品を提供し続けていますが、300年「同じ味」「変わらぬ味」ではないのです。そのときどきの味の流行や志向を考慮して少しずつ味を変えていると言います。
確かに老舗の定義というのは、簡単にいえば「長く残っている店」であり、別に「同じ味を続けている店」ではありませんから、大事なのは、続いているという結果であり、そのための変化というのは理解できます。
兎にも角にも、時代の変化に合わせて企業も変化しないとならない。つまるところ「変化」は事業継続の条件なのです。
変わるもの・変わらないもの
変化は重要。とはいえ、何もかも変えてしまえば良いというものではありません。
変えるものと変えないものがあるからこそ、企業としてのアイデンティティを失わず、時代に適応することができるとも言えます。いわゆる培ってきたコアコンピタンスがあり、それを時代の変化に合わせて応用していく、という。
先の例でいえば、富士フィルムは、フィルムから、デジタル、デジタルから、ヘルスケアへと変化していきましたが、ヘルスケアの商品にはフィルム技術が活かされていたりします。
商品そのものは変わりますが、その背景にある技術や経験、知識は変えない、というか変わりえない。そういう技術、経験は長い年月の中で培ったものですから変える必要も、捨てる必要もありません。間違いなく、自社のアセットとなります。
事業の後継者に自分の分身を求めてはいけない
要は、変えずに活かせるものは活かし、変える必要があるものは変えましょう、という。
言葉にすると当然なんですが、人は本当に変化が苦手。自分が長きにわたりやってきたことは簡単には手放せない。
事業承継において、「後継者にふさわしい人間がいない」という悩みを抱える経営者に聞くと、たいがいの場合、「自分と同じようにできそうな人間」がいないという。つまりは「自分の分身」がいない。
創業のときの事業への想いなのか、いまの技術レベルなのか、取引先とのリレーションなのか、自分と違うポイントはいろいろあると思いますが、どこまでいっても分身なんていない。同じように思い、同じように行動する人間なんて事業承継のタイミングだけでなくこの先探し続けたとしても、絶対に現れない。
自分の分身を求めるがゆえに、その像を押し付けて、いるはずの後継者を殺してしまう、結果的に事業が存続できないケースは意外とあるように思います。
そして、自分とは全く違う人間に引き継ぐのだ、ということは大前提として、違う人間に承継することができる、事業承継を変化するチャンスだと捉えるマインドが必要かと思います。
そのうえで、違う人間、変化する事業を前提として、どう引き継ぐのか?
何かを変える・守るための「言語化・可視化」が大切
親族内の事業承継であれ、従業員への事業承継であれ、第三者への事業承継(M&A)であれ、「考えもやり方も違う人間に引き継ぐ」この事実は変わらないのであれば、事業承継のタイミングで現経営者がやるべき準備とはいかなるものか?
先にも触れたように、商品そのものは変化してしかるべき。
その商品の裏側にあるこれまで培ってきた技術、経験や思いを言語化することでしかないと思います。
創業からの経営者は特に、培った技術や経験というのは、創業からずっと当たり前に対応してきた結果だったりするので、自分のなかに閉じ、言語化されていないことが多いようです。
事業承継を決めるのであれば、相手に求めるよりも先に、まずは自分の頭や心の中の棚卸をして、言語化することから始めましょう。
第三者への事業承継のひとつの抵抗感として、「技術の継承は、何か月も時間をともにして盗み覚えるものだ」みたいな職人気質な考えがあり、見ず知らずのやつにすぐに引き継げるものではない、と判断を下す人もいますが、おそらくそんなことはありません。
事業承継において、引き継ぐ守るもの、を見極めるにも、何かを変えていくためにも、これまでの事業を正確に言語化することは非常に重要なのです。
ただ、先にも述べましたが特に創業者は自分を客観視することなく、やり続けてきてますから、自分の中のものを言語化すること、可視化することは意外と難しい。ただでさえ、自分の特徴も自分でいうのは難しいぐらいぐらいですから。
そんな場合は、外からの意見をもらいながら、整理する、というのはひとつの手法かと思います。
「自分の会社の価値はなにか?」が全くわからないという相談は意外と多く受けます。
事業承継を進めるなかでも、自社の価値が分からなくなったり、他の人にはどう映るものなのか、何を承継すべきか、について悩むことがあればご相談いただければと思います。
執筆/事業承継通信社・柳隆之