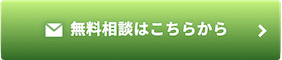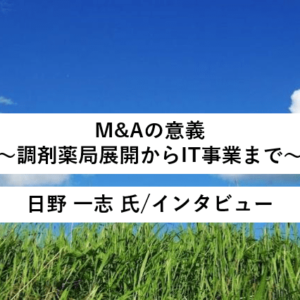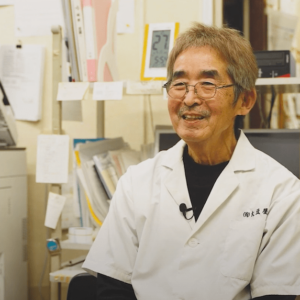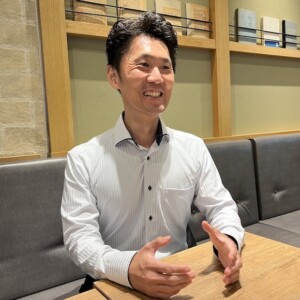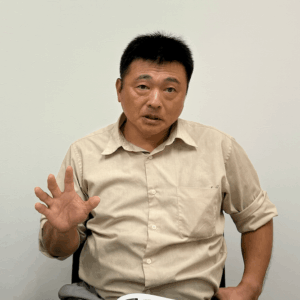【事業承継事例】北海道・水産加工会社の親族内承継|株式会社兼由 代表 濱屋高男氏 インタビュー
ー貴社の事業について教えてください
大正初期に漁業を主な業務として創業し、1962年に法人化しました。法人化した後も漁業を基盤に事業を展開してきましたが、1989年に先代社長のリーダーシップのもと、新たに水産加工業をスタートさせました。
それ以来、漁業事業と水産加工事業の「両輪」による経営を進めてきました。特に水産加工業は、順調に成長を遂げ、安定的な収益基盤を築くに至りました。その結果、現在では漁業事業から撤退し、水産加工業に経営資源を集中させています。
ー社長で4代目になるそうですが、もともと家業は継ぐつもりだったのですか?
大学ではメディア論を専攻しており、マスコミに関わる仕事をやりたいと考えていたので、当時は事業を継ぐつもりは全くありませんでした。ただ、就職活動では希望通りにはいかず、どうしようかと。周りの同期は皆すでに社会人として働いていましたから、やはり焦りもあり、父親と話して、継ぐというよりも東京の事務所で働くところから始めました。
なので、そんなにかっこいいようなものではなく、とりあえず何かやらなきゃ、という気持ちで入ったのがスタートですね。そこから東京に5年。その後は札幌の事務所に転勤して働いていました。
ーどのような心境の変化があって、家業を継ぐ決意をされたのでしょうか?
長く働いていると当然ながら社内の人間との交流も増えて、情もありますが、責任感も芽生えてきたことが大きいです。周りからの期待も感じていましたし、途中で「できません、継ぎません、いなくなります」とは考えられなかった。
また、会社を変えたいとか、良くしたいという気持ちも大きくなる一方で、父に助言をしても、これまでのやり方をなかなか変えようとはしなかった。そうしたところで意見の対立があり、「それならば自分でやった方が早い」と考えるようになりました。新しいことに次々と挑戦して会社を改革したい、と思うようになったということです。
結果的に、2015年に代表取締役に就任し、3年ほど父もいましたが、現在は引退しています。

北海道根室市に本社を構える株式会社兼由
ー社長に就任された当時、会社はどのような状況でしたか?また、どのような課題があったのでしょうか?
当社は、⻑年にわたりサンマや鮭鱒の⼀次加⼯を主⼒事業として発展してきたわけですが、薄利多売の大量生産加工型で、「作ってなんぼ」という世界です。
しかも、このモデルは「8⽉〜11⽉の繁忙期に⿊字を稼ぎ出し、残りの閑散期(12⽉〜翌年7⽉)に発⽣する⾚字を補填する」という季節的収益構造に依存しており、極めて不安定なものでした。
なので、最⼤の経営課題は、この閑散期における⾚字の縮⼩と収益構造の安定化でした。しかし、就任直後から経営環境は急変します。2015年にはサンマの⽔揚げ量が前年の半分にまで激減し、追い打ちをかけるように、翌2016年にはロシア⽔域での流網漁が全⾯禁⽌となりました。この措置によって、「大量生産加工の確保による収益維持」という⼀次加⼯モデルそのものが成り⽴たなくなっていきました。
社員の間にも不安と焦燥が広がっていましたし、時期による業務量の波も激しく、繁忙期は過酷な⻑時間労働に追われ、閑散期にはモチベーションの維持や雇⽤の安定に苦慮する状況が続いていました。
ー凄まじい環境変化ですね・・・そこからの改革はどのように進めたのでしょうか?
そうですね。引き継いだ当初は、メインを維持しつつ新しいことをやりたかったのに、いきなりメインがダメになった状態です。
抜本的な改革が必要だったので、大幅な経費削減と業務合理化で損益分岐点を引き下げると同時に、経営方針を従来の「量」重視から「質と価値」を重視する方向へと転換しました。
2020年には、一次加工事業を大幅に縮小し、高付加価値商品中心の事業へ移行。「レトルト煮付け」商品のラインナップ拡充と販路の拡大に努めることにしました。レトルト煮付けの商品はすでにあったのですが、水産問屋に安く卸す程度にしかやっていなかったのを、直接消費者へ届けるようマーケティングにリソースを割くように転換したのです。
具体的には、BtoB・BtoC双方に向けた多角的な営業活動を展開。年間40回以上の展示会出展や、X(旧Twitter)、Instagram、FacebookなどのSNS活用により、ブランド認知の向上と消費者への直接的な情報発信を強化しました。

新鮮なさんまを自社工場で加工し、レトルト煮付けへ仕上げる製造ライン
ー一番注力したポイントはどこでしょうか?
「とにかく展示会に出て、販路を開拓する」ことです。若い頃、入社して間もない時期に初めて展示会に参加させてもらった経験から、展示会に出展すれば少しでも取引先を開拓できるという手応えは感じていました。ですから、「展示会の回数を増やせば、その分販路も開拓できるはずだ」と考えたのです。
費用はかかりますが、これまでは年に2、3回、それも補助金が出る展示会にしか参加していませんでした。しかし、もうそんなことを言っている場合ではない。社員を1人2人雇うつもりでやるしかないと覚悟を決めました。
ーレトルト食品という新しい事業の柱は、どのようにして生まれたのでしょうか?
もとを辿れば、2007年にレトルト以外も含めた加工品を作るための設備投資をしていました。その設備を利用した形です。先代の時代は、サンマの一次加工がメインでしたから、「小さいサイズのサンマで何か加工品でも作ればいいじゃないか」といった軽い気持ちでサンマのレトルトを始めたようです。サンマ以外で加工品を作ったり、今日のような展開になったりすることは全く想像していなかったでしょう。
これまでの事業とは全く違う、副産物のような扱いでしたから、私が本格的にやろうとした時も、従業員たちは当初は「何を言っているんだ」と思っていたはずです。

看板商品「さんまの旨煮」。レトルトパウチを採用、安全で便利に楽しめる煮付けシリーズとして人気
ー新しい方針を打ち出す中で、従業員の皆さんとの意識改革にはご苦労もあったのではないでしょうか?
やはり一番難しく重要なのは「人」の問題です。社長になって10年になりますが、今もそう感じます。社内にいるのは私よりも社歴が長く、年上の従業員がほとんどです。そのため、当初は新しい方針に対する不安や反発も多少はありました。
私も若かったので「どうして分からないのか」と頭に血が上ったこともありますが、今思えば分かるわけないですよね。
一度で伝わるわけがなく、何度も、本当に何度も繰り返し伝えなければいけないな、と。それが分かるようになったのも、ごく最近のことです。朝礼などで、「なぜこれをやるのか」という目的を、しつこいぐらいに何度も説明し続けることで、ようやく徐々に浸透し始めたと感じています。
ー最後に、今後の事業の展望と、日本の水産業に対するお考えをお聞かせください
日本の水産物は減少しており、昔のように1つか2つの魚種に絞って水産加工業を営むことが難しくなってきています。様々な魚を扱いながら、消費者に受け入れられやすい商品を作らなければ、食べてもらえない時代です。その点、このレトルトシリーズは、時代に合っているのではないかと考えています。
一人暮らしの人でも、忙しい主婦の方でも手軽に作れるし、缶詰よりも持ち運びがしやすく、封を開けるときの怪我の心配もない。安心して美味しく食べてもらえる。
この商品を通じて、少しでも魚を食べてくれる人が増えれば嬉しいです。それが巡り巡って、私たちの事業や経営にも返ってきます。単純に冷凍したりするような付加価値の低い商品を作っているだけでは生き残れません。だからこそ、シンプルに消費者目線に立って少しでも付加価値をつけることで、道は拓けるのではないかと考えています。
インタビュー・執筆:株式会社事業承継通信社 柳 隆之