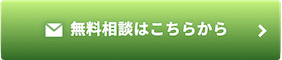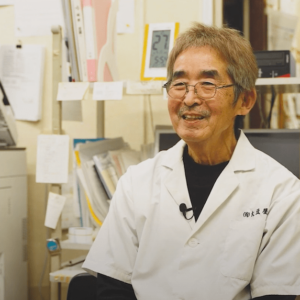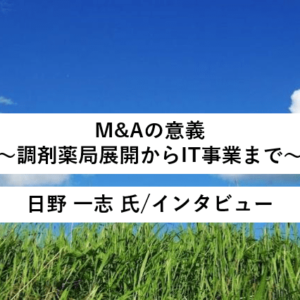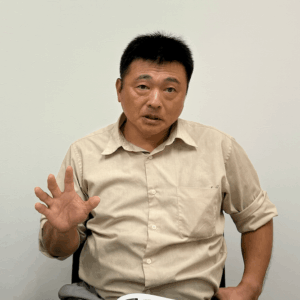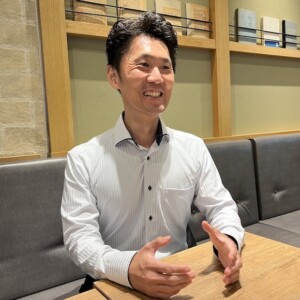【事業承継事例】IT企業の従業員承継|恒和システム株式会社 代表 平野仁美氏 インタビュー
ーはじめに、会社の事業内容について教えてください
創業から46年の歴史を持つ、独立系の中小SES企業です。創業以来、開発現場のパートナーとして、エンジニアを常駐させるビジネスを展開しています。
取引先は大手企業です。非常に長くお付き合いをさせていただいているところも多く、なかには創業以前からのお付き合いで、約50年以上のお客様もいらっしゃいますね。
ーなぜ、それほど長く信頼関係が続いているのでしょうか?
当社は、どの企業の傘下にも入っていない「独立系企業」です。自社の方針と価値観を貫くことで、それが結果的に、長期的で深い信頼関係を築く力へと繋がっているのだと思います。
具体的には、納期や約束を確実に守る姿勢など、社員⼀⼈ひとりの誠実さと真⾯⽬さが現場での高い評価を得ています。
また、当社ではエンジニアの定着率が非常に高く、直近の離職率は2%未満。SES離職率の業界平均は一般的に10〜30%未満と言われていますから、2%未満というのはかなり低い数字です。
長く働く社員が多いので、ノウハウや取引先への理解が蓄積され、質の高いサービスを安定して継続的に提供できていることも、弊社の強みだと自負しています。
ー平野様がこの会社に入社したきっかけをお聞かせください
この会社には事務職として新卒で入社したのですが、⼊社のきっかけは初代社⻑からのスカウトです。
初代社長は、私が学生時代にアルバイトをしていた店の社長の知り合いで、お客さんでもあったんです。店の仕入れから全体の運営まで切り盛りする私の働きぶりを見て、「うちに来ないか」と誘われました。
その当時、当社は横浜支社の立ち上げを計画していまして、「支社を任せたい、会社を作って行って欲しい」とも言われました。私はどうせ就職するなら大きな会社の歯車になるよりも、むしろ小さな会社の大きな歯車になりたい、と思っていたので、それならば、と入社を決めました。
また、やるからには「この会社を一流企業にしたい」と図々しくも大きな野望を持って入社しました(笑)。
ちなみに私が思う「一流企業」とは、上場をしているとか、自社ビルを持っているとかではなく、社員が「この会社に入って良かった」と思える会社です。
ー入社されてからはどのようなことに携わられたのですか?
初代社長から「会社を作っていって欲しい」と言われ、やる気満々で入社しましたので、当初から改善した方が良いと思うことは提案していました。でも、入社してみると「新卒の事務の女の子」という扱いで、とても提案など受け入れてもらえる余地はありませんでした。それでも諦めずに提案し続けたので、面と向かって言われたことはありませんでしたが、陰では生意気だと言われていたようです(笑)。
当時、総務部長も兼ねていた社長直轄の部署でしたので、入社直後から採用や財務、人事・労務など、組織づくりの中心業務に関わっていました。入社2年目で横浜支社の立ち上げ・運営にも携わりました。そうした経験を通して、より一層この会社をもっと良くしたい、という思いが強くなっていきました。
当時の会社は、「組織」というよりも、「技術者集団」でした。技術力さえあれば他はどうでも良い、目の前の仕事さえできればそれで良い、と思っている人がたくさんいました。技術者にはビジネススキルは不要と思っているのか?という人も少なくありませんでした。
そこで人材育成についても何度か提案しましたが、初代社長は人材育成という考え方はあまりなく、「会社に育ててもらうのではなく、自分で学ぶものだ」「メシのタネは自分で得るものだ」という考え方でした。確かにその通りだと思うのですが、組織全体として成長していくためには、個人の努力や資質だけに頼っていて良いのか、と疑問にも思っていました。また実際問題、人材育成はお金がかかる、ということもネックでした。

ー実際に会社全体を変えることに着手したのはいつ頃になりますか?
2012年の2代⽬社⻑の就任と同時に、役員として経営に参画することになったタイミングです。当時の2代⽬社⻑は経営に対してあまり関⼼を持っておらず、そのおかげで私が主導となって、以前から構想していたさまざまな取り組みを実⾏に移していきました。
主には、「人材育成」と「組織体制の改革」です。
「人材育成」はかねてからの重要テーマでしたが、資金不足を理由になかなか実現できずにいました。
取締役となれば責任を取ることができますので、その費用を捻出するために、税務や労務業務の外部委託をやめ、私の知識を活かして内製化しました。その浮いたコストを社員の教育に投資して、Eラーニングや外部研修、新人研修制度などを整備しました。
また同時に経費の見直しも進め、社員の給与水準を維持しながら、黒字化と無借金経営を実現することができました。
「組織体制の改革」については、上下関係のある組織を変えました。SESという事業の特性上、社員がそれぞれクライアント先に常駐勤務することが多いのですが、給与や賞与は本社の部長職や課長職といった役職で決まっていました。現場では下のポジションだけど本社では課長だから給与が高い、という現象が起きて、それは違うんじゃないかな、と。そういった矛盾を変えたいと。
フラットな体制にしたうえで、「自分たちの会社は自分たちでつくる」という意識を作るため、どういったお金の流れで自分たちの給与が決まっているのか分かるように「経営情報の公開」も実施しました。
会社の利益構造やコスト内訳はもちろん、社員一人ひとりの売上や利益、コストまで、経営情報を全社員に公開しました。それらを社員が知って理解することが、主体性につながるとも考えたからです。
実際に一人ひとりが業務効率を考えるようになり、残業代も減って、収益が上がりました。それによって決算賞与を出すこともできました。そうすると、自分の頑張りが成果になって返ってくる、と社員も実感して、俄然やる気が出るわけです。
いまでも「社員ファースト」の考え方を徹底し、評価制度や決算賞与の分配方法など会社の大きな方針は、社員の意見をもとに決めています。
ー新しい試みとなると、導入するにあたって現場からの抵抗はありませんでしたか?
それは、少なからずありました。経営情報の公開については、役員の中から反対の声が上がりました。そんなことは社員に知らせるべきではない、と。また研修については役員だけでなく現場からも。現場を抜けて研修に行くことは、費用だけでなく売上も落ちる、と。
さらに、費用がかかる外部研修だけでなく、私が講師になって毎月社内研修も始めたのですが、これについては二代目社長から「無理だ」「続かない」とも言われました。
でも、社員が経営者目線を持つためには、経営数字の公開は必要だと思っていましたし、人材育成は絶対に不可欠だと思っていたので、とにかく実行しました。
この仕事は、⼈との関わりが少ない仕事のように思われがちですが、実はお客様の要望を汲み取ってシステムというカタチにするのが仕事なので、コンサル的な能力やコミュニケーション能力は重要なのです。

ー2023年に「従業員承継」という形で事業を引き継ぎ、代表取締役に就任されました。そこからの取組みはありますか?
社員⼀⼈ひとりの夢や希望、将来どうなりたいかなどを聞くため、全社員と個別⾯談を⾏いました。⼀⼈ひとりの夢や希望が叶えられる会社になるためには何をすべきなのか知るためです。
それにより、社員の思いやビジョンを汲み取ることができ、会社として「今何をすべきか」「どこを変えるべきか」に正⾯から向き合うきっかけとなりました。
また、新入社員から3年目までの社員のフォロー体制を強化しました。簡単に言うと、毎月一回ご飯を食べながら仕事やプライベートの話をしたりする同期会のようなものなのですが、同期同士だけでなく、先輩と共同開催をしたり、若手の繋がりを深める取り組みです。その結果、若⼿社員が今どんな悩みを抱えているのか、⽇々どんなことで苦労しているのかを、早い段階で把握できるようになりました。
普段の業務の中では⾒えにくい声や、上司にも⾔いづらい本⾳を直接聞くことで、現場で起きている問題や課題をリアルタイムで捉えることができます。こうした情報を早期にキャッチすることで、必要なサポートや制度の⾒直し、業務の改善などをスピーディーに⾏うことができ、社員の不安や不満が蓄積する前に⼿を打つことが可能となりました。
そのお陰か、働きやすさが向上し、若⼿社員の定着率も非常に高くなり、離職率1.9%という⽬に⾒える成果にもつながっています。
社員全員対象の社内研修も月1回行っていますので、そこが学びの場でもあり、直接社員とコミュニケーションを取る場にもなっています。
また、これまで以上に教育に力を入れています。
コミュニケーション力はもちろん、リーダーシップやフォロワーシップ、自分の成長と会社の成長を同期させる考え方など、社員一人ひとりが活き活きとこの会社で働いていけるようになるための教育を実施しています。
ーなぜそこまで人にこだわるのでしょうか?
社員根性が抜けないんだと思います(笑)。自分が社員だったときに嫌だったことや、こうだったら良いのに、と思うことを改善している感じですね。
入社当初から採用担当として多くの社員に関わってきましたが、自分が採用に尽力した社員が早期に退職を選ぶ姿を見るのは、非常にショックでしたし、「なぜ気づいてあげられなかったのか」「もっとできることがあったのではないか」という強い後悔もありました。
私たちのような業種は、結局「人」がすべて。人が減れば、当然売上も下がる。だからこそ、人を大切にしなければ、会社として成り立ちません。
ー会社の将来については、どのようにお考えですか?
次の世代の経営者については、従業員の中から手を挙げて欲しいと思っています。
ただ、会社を一人で背負うと思うと、負担が大きすぎて手が挙げられなくなってしまうかもしれないので、一人が全部を担うのではなく、役割を分担しながら支えていける体制をつくることが現実的だと感じています。そのためにも、ある程度は仕組み化していく必要がありますね。
大切なのは、忌憚なく何でも皆で話し合える状態にしておくことだと思っています。
私自身は、経営者としての原動力は何かと聞かれたら、正直なところ良くわからないんです。強いて言えば「やりたいからやっている」。「好き」に理由はない、というのと同じような感じでしょうか(笑)。
ー最後に、事業承継を考える経営者に向けてアドバイスをお願いします
会社を引き継ぐにあたっては、まず「どんな会社にしたいのか」というビジョンを明確に持つことが大切だと思います。
「⾃分が経営者だったらこうするのに」と考えていたことを、実際に形にしていくタイミングだからこそ、自分自身の判断軸をしっかり持つことが求められます。
ただし、稲森和夫さんが常々仰っていた「無私の心」は、経営者という何でもできる強い立場だからこそ、しっかり心に刻んでおかなければならないと思っています。
それに独断専行ではいけません。大きなことを実現するには、周囲の協力が不可欠ですから。社内外の立場の異なる人の声に耳を傾けながら、柔軟に取り入れていく姿勢が必要だと思いますね。
特に、「若者」「⾺⿅者」「よそ者」、そしてその分野に⻑く関わっていない⼈の意⾒には、固定観念にとらわれない新鮮な視点が含まれていることが多く、そういった声の中に、事業の見直しや改善のヒントが隠れていることも多いと感じています。
また、日々の業務で当たり前になっている「常識」についても、改めて問い直す姿勢が必要です。異なる価値観を持つ人との対話や交流を通じて、思い込みに気づいたり、新しい発見や課題意識が生まれることもよくありますから。
そして最終的には、自分自身の価値観を反映させながら、自分らしい経営スタイルを築いていくことが大切だと感じています。
過去の延長ではなく、新たな方向性を示すことで、事業を持続的に成長させていけるのではないでしょうか。
インタビュー・執筆:株式会社事業承継通信社 柳 隆之